のぼり旗には防炎加工の有無がありますが、ほとんどの場合、見ただけではそれを判断することは困難です。
一方、設置場所によっては防炎加工されたもののみを設置できるケースもあることから、のぼり旗を設置したい場合には、それがどんな生地でどんな加工が施されたのかを知る必要があります。

そこで消防法の規則で義務付けられているのが防炎表示で、その製品に防炎効果があるのか否かを判断できます。テストをクリアして基準を満たすと防炎表示が可能となり、万が一火災が発生してそののぼり旗に炎が写ることがあっても、防炎加工により延焼を防ぐことが期待されます。
消防法の規則による視察が行われることがあっても問題無しとされクリアできるのはもちろんのこと、訪れたお客さんがその表示を見れば万が一の火災に陥っても安心だと思うことができます。これにより店舗ならば安心して来店でき、また利用してみたいと言う気持ちにさせるなどリピーターの増加や顧客満足度の向上、そして何より安心安全な環境を構築することができます。
多くの人々が出入りする店舗だからこそ、安全に対しては常に配慮しておきたいところですが、これらの表示がその第一歩となります。
記載例を見ながら簡単に書ける
正式に認可されたのぼり旗の防炎表示をするためには、日本防炎協会に交付申請書を提出して受理される必要があります。
認可されると照会ナンバーなどが表記された補助ラベルが交付されるので、対象ののぼり旗に縫い付ければ、それが認可された防炎加工が施されたものだと証明できます。
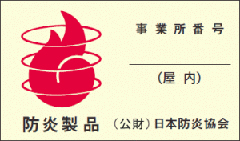
交付申請書は、日本防炎協会の公式ウェブサイトからファイルをダウンロードできます。業種や物品の区分があるので、その中から対象のファイルを選びます。それを印刷して必要事項を記入すれば完成します。
ここで書き方が気になるところですが、同じページからダウンロードできる記載例を見ながら行えば簡単です。注意事項が記載されているので、それに従って記入して行けば問題ありません。
提出を行うと規定に沿った燃焼試験が実施され、合格すれば晴れて照会番号や補助ラベルが発行され、対象の製品に貼付したり、同協会が認めた防炎加工が施されていることをアピールすることが可能になります。
利用する際に安心感を与えられると共に、それを必要としている顧客に対して商品に付加価値を与えることもできます。正しい申請を行うことで手続きがスムーズに進行し、早期に認可を受けることが可能です。